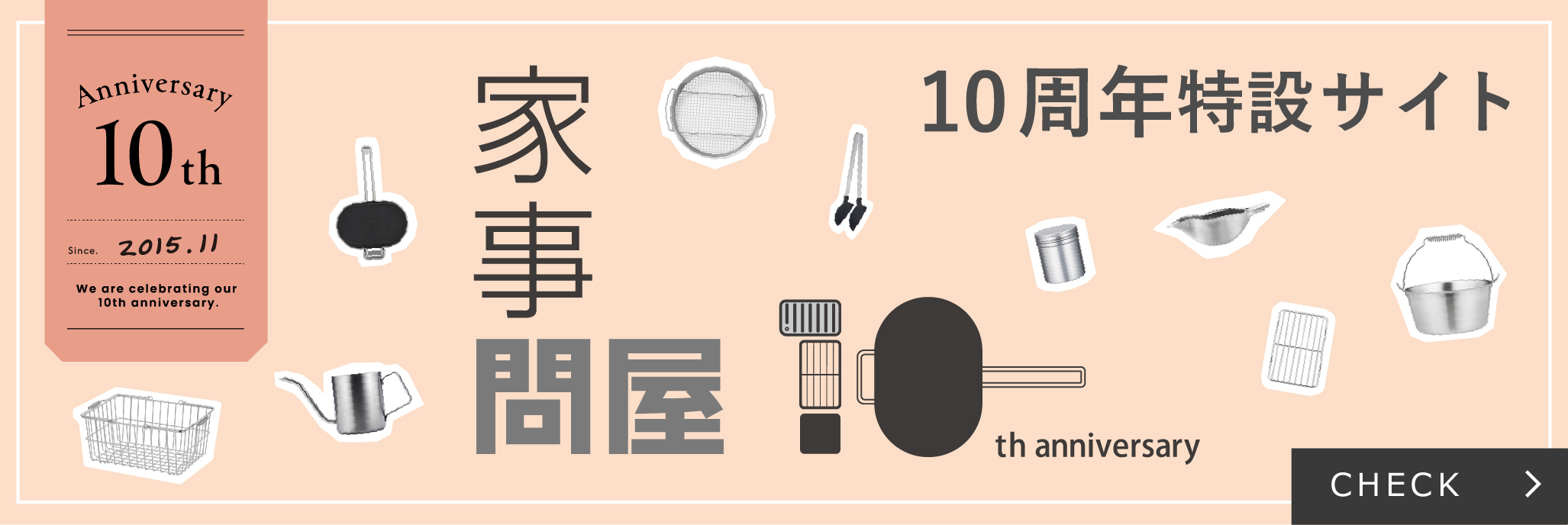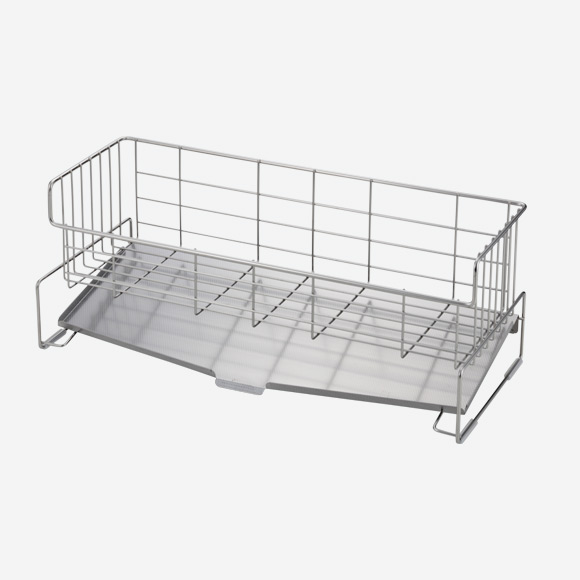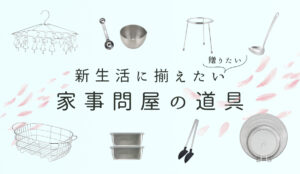【こうばを訪ねて vol.14】たった1台の機械から始まったシリコン製品のパイオニア
文/金子 美貴子

金属加工品の一大産地、新潟・燕三条で30社以上の工場と一緒に家事道具をつくる、家事問屋。毎日の暮らしの「ひと手間」を助ける道具をお届けしています。
私たちが大切にしていることは、道具と共に、つくり手の想いもみなさんへ届けること。
そのために日々工場を訪ねて、既存製品の反響を共有しながら、新たな製品づくりを進めています。
今回訪ねたのは、プラスチック製品の成型・加工を得意とする有限会社大泉合成。創業56年の歴史を誇る、プラスチック製品・シリコン製品製造のパイオニア的存在です。
家事問屋では、ブランド立ち上げ当初から販売している「シリコンスパチュラ」を製造していただいています。

キッチン用品に欠かせないシリコン製品のメーカーとして会社をけん引する代表取締役社長の大泉航亮さんにお話を伺いました。
たった1台の機械で創業
―異業種を経験されている2代目社長は少なくありませんが、製造業へ大きなご転身ですね。
そうかもしれません。私は3人きょうだいですが男性は私だけで、当時は長男が家業を継ぐのが当たり前という時代。東京に出ましたが、いずれは地元に戻ることが暗黙の了解でした。就職活動で一般企業からも内定をもらいましたが、どうせやるなら、やりたい事をしたいと児童福祉の仕事を選びました。仕事にはやりがいを感じていましたし、とてもよい職場でしたが、ある時、父から戻るように言われて。戸惑いがなかったとは言えませんが、そういう宿命と受け入れましたね。
―製造現場に入り、ゼロから経験を積んでいったのですね。2代目としてどのようなことを意識されていますか?
創業者である父は、20歳の時に1台の機械だけを元手に会社を興したバイタリティーがあり、明るくエネルギッシュですが、自分は全く異なるタイプです。会社には自分よりも長く勤めていて、私より現場に詳しいスタッフもいます。なので、私は私なりのやり方で、従業員やお客様、関わってくださるみなさんへの感謝の気持ちをもって接することを心掛けています。

―たった1台の機械から始まって、ここまで成長されたのですね。
「仕事は与えられるものではなく、自分で作るもの」とよく聞きますが、そんな言葉を体現してきたのが父です。人に勧められて機械を買ったはいいけど、何のノウハウもない。周囲に頼み込んでなんとか仕事を取ってきて、機械の使い方を教わりながら製造し納品する。習得したい技術があれば、他社にも頭を下げて教わる。
そんな体当たりを繰り返しながら技術を身に着け、業務を拡大してきました。当社の歴史はそのまま挑戦の歴史といえるかもしれません。「大泉に頼めばうまくまとめてくれる」、そう思ってもらえるよう日々取り組んでいます。
―大泉合成と家事問屋のつながりのきっかけを教えていただけますか?
まず、下村企販さんと初めて仕事をしたのが15年ほど前。その時に手掛けた、少し持ち手が長いシリコンスプーンシリーズが大ヒットしました。私が東京にいた時に、ロフトなどでも見かけたのを覚えています。
その後、2015年に家事問屋が立ち上がり、ブランドの第1弾の製品ラインナップとして「シリコンスパチュラ」の試作で久保寺さんにお声がけいただいたのが最初です。

長年の知見から生まれた「シリコンスパチュラ」
―「シリコンスパチュラ」の製造はどのように進めていったのでしょうか。
最初に久保寺さんから相談があった時は、まず「燕三条らしく、持ち手は丈夫なステンレス製にしたい」、そして「シリコン部分だけ取り換えられるようにしたい」とのことで、課題は「シリコンの硬度」と「抜け止めの工夫」の2点でした。

シリコンの硬度については、異なる硬度の試作品をいくつか提案しました。同じ材料でも配分や厚みでの違いで柔らかさは変わりますが、それまでの経験から、適切な厚み、硬度がだいたいイメージできていたので、シリコン部分の試作品づくりではそれほど悩まなかった印象です。ただ、久保寺さんは、その中からどの硬度で行くか決めかねたようで、試作品をさまざまなシチュエーションで使用してみて実験を重ねるなど、苦心されたようですね。

「抜け止めの工夫」については、なかなか大変でした。シリコン部分が取り外せることがポイントの製品ですが、使用中に簡単に抜けてしまうようでは困ります。そこでステンレスの持ち手のシリコンに差し込む部分に引っ掛かりを作りたい、ということでした。実際には、ステンレスの部分が真っすぐのままでも使用中に抜ける心配はほぼありませんでしたが、「抜けやすそうな感じがする」という印象を与えることが問題です。

適度な引っ掛かりを作るにはどうすればいいのか。金型を丸ごと作り直すのは勿体ないですし、結構悩みましたが、板状の先端部分に上下から圧をかけてサイドにわずかな膨らみを作ることで、「差し込みやすく、抜けづらい」形状を実現することができました。これは当時の機械で出せる、強度に影響しないギリギリの薄さを追求したものでしたね。これも何度もテストを重ねて、ようやくGOサインが出ました。
シンプルな方が難しい
―家事問屋に対してはどのようなイメージをお持ちですか?
シンプルさで目を引くブランドだなと思います。ショップで見かけると、世界観が伝わるような見せ方になっていて上手だなと思いますし、全体的にデザインの統一感があって品がある印象です。
メーカーの立場で言わせていただくと、シンプルな方が難しいですね。細部の仕上がりが品質に影響します。
―どこで品質の差が生まれるのでしょうか?
他社と使う機械は同じだったりしますから、金型の出来で大きく左右されると思いますね。技術力の高い金型屋さんにお任せすること、そして製造工程を厳密に管理することが大切だと思います。

あと家事問屋の製品は、使い手のことを考え抜いていますよね。例えば、「シリコンスパチュラ」も、業務用だったらヘラ部分と持ち手は一体型が現在の主流です。その方が洗いやすいし清潔を保ちやすいですしね。
でも家事問屋では、衛生面への配慮もありつつ、「ながく使っていただくこと」を前提としています。多少コストがかかっても、消耗部分のパーツだけ取り換えられる造りの方が、長期的に見て使い手にとってエコであるという考え方。これは私たちにはなかった発想だなと思います。

さまざまな条件がある中で、最大限に使い手の立場に立つというのはなかなかできないこと。そういったスタンスも家事問屋らしいと感じます。
燕三条で生まれ育ったことが今では誇り
―最後に、産地への想いをお聞かせください。
私の子どもの頃とは違い、燕三条のものづくりをすごいと言っていただけるようになったことに時代の変化を感じています。自分にとっては当たり前にあった環境が、全国的にもユニークな産地として認知されるようになって、そんな町に生まれ育ったことを誇りに思うようになりました。

父の時代は、メーカーは「下請け」「仕事をもらう側」という立場で、あまり物を言える雰囲気でもなかったようです。とはいえ、お互いストレートな物言いでケンカになることも多かったようですが(笑)「謝れば許してもらえた」というおおらかさもあったようです。そういった関係性も時代とともに変わってきているのかなと感じます。
自分自身、燕三条のことを十分に理解しているとはまだまだ言えませんが、産地の財産を守るために、日々の仕事を通じて情報発信もしていければいいなと思っています。

機械1台で創業し、体当たりで製造技術を学びながら着実に事業を拡大し、シリコン製品のパイオニア的存在にまでなった有限会社大泉合成。
新しいものづくりを目指す家事問屋の心強いパートナーです。
世界に誇る燕三条クオリティを次世代へとつないでいくため、工場と手を携えながら、今後もより良い製品づくりに取り組んでまいります。

読みもの登場製品

シリコンスパチュラ 15
価格:1,320円(税込)

シリコンスパチュラ 20
価格:1,540円(税込)

シリコンスパチュラ 24
価格:1,980円(税込)